秋バテの原因

こんにちは😄
ここ最近、寒暖差が激しくて何を着て外に出ればいいか迷いますね😅

そこで、今回は秋バテの原因について書いていきます!!
夏から秋にかけての季節の変わり目に生じるさまざまな不調は、
一般的に「秋バテ」と呼ばれています。
医学的には、「秋バテ」の明確な定義はありませんが、
夏の疲れや、昼と夜との寒暖差が
大きくなることで生じる不調を指します。

秋バテには身体と心、両方の症状があります😱
秋バテには、以下のとおり主に身体的症状と精神的症状があります。
■【主な身体的症状】
- □疲労倦怠感
- □食欲不振
- □便秘、下痢などの消化器系の不調
- □立ちくらみ
- □めまい など
■【主な精神的症状】
- □やる気、集中力の低下
- □抑うつ感
- □イライラ
- □不眠 など
こうした症状が起こりやすくなる主な原因として、次の3つが挙げられます。
- 1.自律神経の乱れ
- 2.栄養の偏り
- 3.胃腸など消化機能の低下
秋バテの原因の1つ目は、自律神経の乱れです。

自律神経は、全身に張り巡らされている末梢神経まっしょうしんけいの一つで、
意思に関係なく24時間働き続け、
体温調節や血圧、呼吸数のコントロール、
消化や発汗など、
さまざまな体の機能を整える役割を担っています。
自律神経には環境の変化に体を適応させる働きもあり、
気温が高くなると副交感神経が優位になり、
反対に低くなると交感神経が優位になる傾向にあります。
暑い夏から涼しい秋への季節の変わり目は、
主に体温調節のために“副交感神経モード”から“交感神経モード”へと
自律神経のスイッチが切り替わる時期といえます。
暑い日があったかと思えば、
急激に気温が低下したりと環境が揺らぎやすいのも、
季節の変わり目の特徴の一つです。

また、1日の中で、朝から日中の活動時間帯は交感神経モード、
夕方から夜間の休眠時間帯は副交感神経モードと、
自律神経は波のようなリズムを持っています。
しかし、環境の変化などによって、
自律神経が乱れて調節がうまくいかなくなったり、
交感神経が優位な状態が続いてうまくリラックスできなくなったりすると、
先に挙げたようなさまざまな身体的・精神的症状を引き起こす
要因の一つになると考えられます。
秋バテの2つ目の原因である「栄養の偏り」は、

主に夏場の食生活によって引き起こされます。
夏は暑くて食欲が湧かないために、
そうめんのような喉越しの良い食事に偏りがちです。
そうした食事を続けていると、
どうしても糖質の摂取量が多くなります。
また、甘いジュースやアイスクリーム、
アルコールなどを多く摂る傾向にある人も要注意です。
糖質の摂取量が過剰になると、
腸内に存在する日和見菌ひよりみきんの一種「カンジダ菌」
が増殖しやすくなります。
「カンジタ菌」が増殖すると、
本来は酸性であるべき腸内がアルカリ性に傾き、
悪玉菌が増える要因になると考えられています。

腸内環境が乱れることによって、
さまざまな不調が生じることになりかねません。
その一方で、ビタミンB群やミネラル、
たんぱく質などは不足する傾向にあります。
ビタミンB群やミネラルは「細胞の中の電池」と呼ばれており、
細胞内でエネルギー生成のために働く
ミトコンドリアの代謝を促進するうえで大切な栄養素です。
これらの栄養素が夏の間から不足した状態が続くと、
秋になる頃に“電池切れ”を起こすことになります。
その結果、疲労倦怠感といった症状が現れやすくなるのです。
秋バテの3つ目の原因である「消化機能の低下」は、
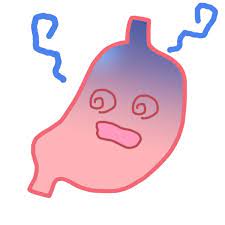
栄養不足も招きやすいので要注意です。
暑いからといって冷たいものを摂り過ぎると胃腸が冷え、
消化器系の働きが悪くなりやすくなります。
この結果、食欲がなくなり、栄養を十分に摂ることができなくなって、
疲労倦怠感が起こりやすくなるという悪循環に陥るのです。
以上の事が秋バテになる原因とされています。
次回は、秋バテ予防について書きますので、
秋バテ気味だなと思う方は
ぜひ、そちらもご覧ください😌
Tags:






