寒暖差アレルギー

こんにちは😄
季節の変わり目になり、体調を崩していませんか?
昼間は暖かいのに、夜になると急に寒く感じ、
くしゃみ、鼻水、鼻づまりで鼻がムズムズすることはありませんか?
このような不調を感じたら、
「寒暖差アレルギー」を疑っても良いかもしれません。

寒暖差アレルギーとは何か、特徴や対処法などについて、
書いていきます😌
●原因不明の鼻水・鼻づまり
くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどアレルギーに似た症状が出るものの、
特定の原因(アレルゲン)によって引き起こされるアレルギーでもなく、
熱っぽいけれど風邪でもない症状を
「寒暖差アレルギー」と言い、
医学的には「血管運動性鼻炎」と呼ばれます。

花粉症やアレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患は、
花粉、ホコリ、ダニなどが原因となるアレルゲンによって
免疫反応が起こりますが、
血管運動性鼻炎は検査をしても明確なアレルゲンが見つかりません。
また、風邪のようにウイルスに感染して炎症を起こすわけでもありません。
このような原因の分からない鼻水、鼻づまりなどの症状が出るのが、
血管運動性鼻炎です。
風邪との大きな違いは、
鼻水がサラサラした水っぽい状態であることと、発熱がないことです。

また、アレルギー疾患によく見られる目や皮膚のかゆみなどの症状もなく、
人にうつることもありません。
■寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)の特徴
・温度差によって鼻水や鼻づまりなどの症状が出る
・サラサラした水っぽい鼻水が出る
・熱はないのに、だるいなど風邪のような症状がある
・目のかゆみや充血はない
・鼻がムズムズする
寒暖差の原因
寒暖差アレルギーの症状は、
温度差が7度以上になると出やすいとされています。
原因はまだ解明されていませんが、
温度差によって自律神経のバランスが崩れることで
発症すると考えられています。

自律神経には交感神経と副交感神経があり、
相反する作用を持つこの2つの神経がバランスをとって
体内の臓器や血管などの働きをコントロールし、
体内環境を調節しています。
鼻の粘膜にある血管の収縮・拡張も自律神経によって
コントロールされています。
激しい温度差が刺激になってこの調節がうまくいかなくなり、
鼻水が出やすくなってしまうのです。
寒暖差アレルギーの対策
寒暖差アレルギーは温度差が刺激になるため、
例えば寒い戸外に出て鼻水が出た場合、
室内で体を温めれば症状は抑えられます。
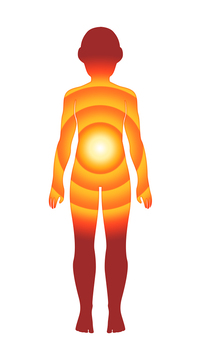
できるだけ温度差やタバコの煙、大きなストレスなど、
刺激になるようなことを避けると良いです。
また、
日常では、温度差をなるべく小さくするように心掛け、
血流を良くすることが大切です。
衣服などでこまめに体温調節ができるように
羽織れるものを携帯しておきましょう。

マスクも鼻の粘膜に触れる冷気を遮断するので効果的です。
また、血流を良くするためには、
太い血管が皮膚の表面近くを通っている首・手首・足首の“3つの首”を
温めると効率的です。

食事ではショウガなど体を温める食材を積極的に取り入れましょう。
さらに、筋肉を維持するためにも、
血流を良くするためにも運動が大切です。

自律神経のバランスを整えるという意味では、
就寝の1時間くらい前に入浴し、
軽いストレッチをして深部体温(体の内部の体温)を上げてから寝床に入ると、
深部体温が下がるタイミングで眠りにつくことができ、
質の良い睡眠が取れます。
睡眠のリズムが整うと自律神経のバランスも整ってきます。
自律神経を整える健康的な生活を送ることは、
寒暖差アレルギーの予防だけでなく、健康全般にとって有益です。
寒さなどの環境刺激に負けない丈夫な体は日ごろの
生活習慣の積み重ねによって作られます。
できることから改善していきましょう。
Tags:






